つい先ほど、ランニング中に「いまだ成らず」をオーディブルで聴き終えました。
あまりにも良くて感動し、誰かに言いたくてたまらないのでご紹介させてください。
書籍も買います。
— 4n5_ランニング@2/23読売犬山ハーフマラソン (@4n5_Running) February 4, 2025
本書籍との出会いと、聴こうと思ったきっかけ
こちらの書籍は、将棋界を取り上げたノンフィクション作品です。
50年強の移り変わりを、色々な棋士の視点を通して語られています。
昨年末、大型書店で偶然見つけました。
年明けにオーディブルで配信されることがわかり、その場では購入せず楽しみに待っていました。
普段はビジネス書ばかりで、ノンフィクション系を読むことはほぼありません。
ただ、小学生の6年間将棋に取り組んでいたこともあり、いまだに目に入れば気になってしまいます。
同じ将棋教室に、現在A級で戦う稲葉陽八段が在籍していました。
同級生なのですが当時から異次元の強さで、「天才ってこういう人なのだろう」と幼いながらに実感したものでした。
そういった経緯もあり、本作品をオーディブルで聴くことにしました。
結果、あまりにも感動したので、文章にまとめようと思った次第です。
全編素晴らしいのですが、感動した部分を大きく2点取り上げたいと思います。
天才たちの挫折と葛藤、その後の「悟り」
まず一つ目は、天才達が挫折し、その後色々な葛藤を乗り越えていく場面です。
「諦めと悟りの違い」は、僕がここのところよく考えているテーマなのですが、答えの一つがここに書かれているように感じました。
1年に4人しか棋士となることができない棋界は、天才しか存在しない世界です。
その中にも羽生さんや藤井さんのように、時に天才の中の天才が現れます。
これまで天才として生きてきた他の棋士は、自分が超えられない壁に出会った時どういう反応を示すのか?
結論としては、僕たちと同じように狼狽し、「なぜ同じ時代に…」と呪い、スランプに陥ってしまうようです。
その後酒やギャンブルにのめり込み、二度と浮上できない人がいる一方で、タイトルを取るような棋士は、一定期間後に舞い戻ってきます。
それを分けるものは、内面の変化。
一旦天才の存在を受け入れ、勝敗とは別に、自身の棋風を刷新し、新たなものを取り入れる。
すなわち、自身の棋力を高めることに集中するのです。
相対評価から絶対評価へ、あるいは承認欲求から自己実現欲求へと昇華されるということです。
そこにネガティブな想いはない。
「感情面にネガティブなものがあるかどうか」
これが「諦め」と「悟り」を分けるものなのだと感じました。
作者のインタビュー力と、表現力
もう一つは、作者のインタビュー力と、その表現力です。
「心の中を読めるのか?」、あるいは「本人が書いている?」と思わされるほど、人の内心を抉り出しています。
上でも触れたように、棋士の内面には時にネガティブなものがあり、人に話したくないものもあるでしょう。
それをどうやって聞き出したのか。
作者のインタビューのスキル、そしてそれを遺憾なく発揮するのに、棋士から受け入れられる人間力があったと思わざるを得ません。
そしてそれらを紙面に載せるにあたり、空気感や季節、場所などと絡めてストーリー性が高められている。
脳内にビジュアルが浮かぶ描写ながら、同時に「美しさ」も感じるのです。
写術的でありながら、抽象的でもあるのです。
本来対角線上にある表現を、両立させている。
自らも最近、ノンフィクションを少し書いています。
だからこそ、その圧倒的な筆力に唖然としました。
プロの力を、まざまざと見せつけられる文章です。
まとめ
以上から、中身とその表現力が高い次元で融合する、史上稀に見る傑作でした。
本も買って、今一度読み直します。
本棚に一生残る本となりそうです。
25歳で七冠を制した羽生善治。
勝敗の数を超えたその強さと人生を、
藤井聡太らトップ棋士たちとの闘いを通じて描く。宇宙のように広がる盤上で駒をぶつけあう者たち――。
本書は、名対局の一瞬一手に潜むドラマを見逃すことなく活写してゆく。
中学生で棋士となった昭和。勝率は8割を超え棋界の頂に立った平成。
順位戦B級1組に陥落した令和。三つの時代、2千局以上を指し続けた
羽生善治、そして共に同じ時代を闘ったトップ棋士たちの姿を見つめながら、
棋士という“いきもの”の智と業をも浮かび上がらせる。
「週刊文春」連載時より大きな反響を呼んだノンフィクションに
新たな取材、加筆を行った堂々の一冊。【主な登場棋士】
米長邦雄/豊島将之/谷川浩司/森内俊之/佐藤康光/深浦康市/渡辺明/藤井聡太
Amazon本書紹介ページより引用
オーディブルは30日間無料です。
一度試しに聞いてみても良いかもしれません。

ランニング中のオーディブル利用については、以下の記事にまとめています。
よろしければお読みください。
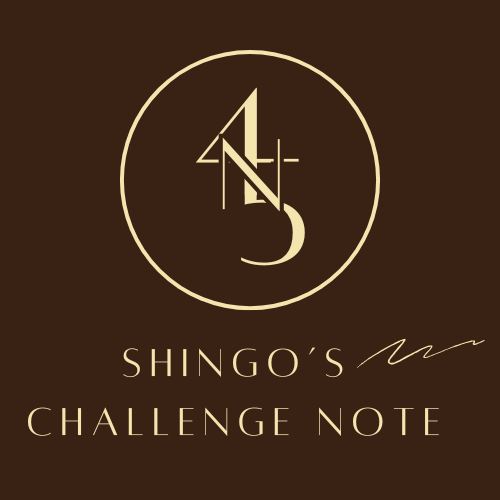
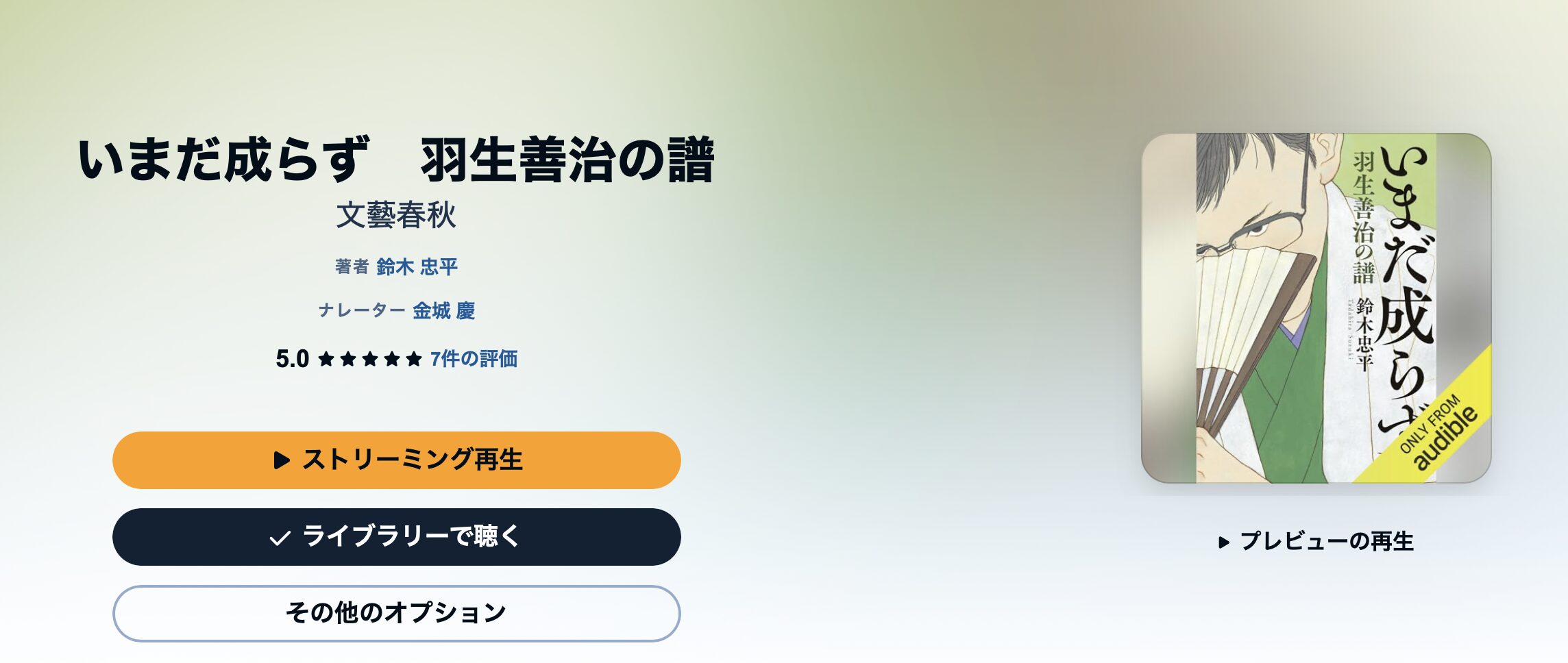




コメント